「幸せ」とはなんだろう。自分は人付き合い、自分自身との付き合いがうまくなく、
幸せを感じるのは夢のまた夢、そう感じて日々を過ごしてはおりませんか?
そんな方にお勧めな書籍が今回紹介する「鏡の法則」(著者:野口 嘉則さん)に
なります。
他人との付き合いがうまくいかない方はもしかしたら過去の自分と決別ができていない、
育ってきた環境に問題があるのかもしれません。
どういった方に当てはまるのか、その対処法はどうすればいいのかが本書には書かれております。
購入はこちらから (著者:野口 嘉則さん)
この記事でわかること
- 「鏡の法則」の解釈と感想がわかる
- 特に重要なピックアップ項目がわかる
ずっと心にモヤモヤを抱えて自分を嫌いになっている方にぜひ読んでもらいたい一冊になります。
それではまいりましょう!
許すとはどういうことなのか

「許す」とはどういうことなのか、本書では以下の通りと定義しております。
「ゆるす」とは、過去の出来事へのとらわれを手放し、相手を責めることをやめ、
今この瞬間のやすらぎを選択することです。
参考:「鏡の法則」48ページ
本来許すことは相手のためにするものと感じるものですが、本書は相手ではなく、
自分のために相手の行いを許し、過去の出来事にとらわれずに前を向いて歩き出すとしております。
そのため、誰か許さないということはその出来事に縛られ続けるためその時点から
前に進めなくなってしまうのです。
人は「許さない」の積み重ねで徐々に鎖に縛られて心の自由を奪われて、幸せを失っていってしまう
という過程を追ってしまうのです。
「許す」という行為が相手のためではなく自分のためという発想はなかなか出てきませんでしたので
新鮮味を感じました。
相手は素直に非を認め謝罪してきたのに自分が許さなければ、自分が先に進めなくなるという
損な役回りになってしまいますから、普段人の行いを「許す」ことの重要性がわかるかと思います。
親との間に境界線を引けない人たち

前項目の「ゆるす」という行為を普段からできる方はそもそも幸せな状況を掴んでいる方が
多数いらっしゃると思いますが、「ゆるす」ことができない方には他人と自分に境界線を
引けないためと本書では語られております。
さらに、他人と境界線を引けない方の原因は親との間に境界線を引けないと言及しております。
なぜ親との間に境界線が引けないのか、それは育てる親側に問題があります。
というのは、過保護な親や過干渉な親に育てられた人の場合が多く当てはまります。
例えば幼少期の頃に子供どうしのいざこざに親が口出ししてきたり、障害を先回りして
取り除いてしまったり、進路や将来の夢に大きく干渉してきたり等々です。
過保護な親の子ほど境界線が引けなくなるため、自分の考えで行動しなくなり
相手の言動や要望に振り回されてしまいます。
親との間に境界線を引けないまま大人になると、他者との間に境界線を引くことも
難しくなるので、他者の言動に振り回されたり、他者の言動に傷つきやすくなったりしてしまう
参考:「鏡の法則」54ページ
他者との間に境界線が引けず、常に「ゆるさない」状態の方に待っているものは
その組織から身を引いて辞めたり、いなくなったり、最終的に自分の殻に引きこもってしまったり、
おそらく自分もしくは周りにも身に覚えがある方がいるかもしれないですが、
そういった状態になってしまいます。
どうやって境界線を引けばいいのか

ではもう成人した方々はどうやって境界線を引けばいいのか、本書ではその方法が
2つ記されております。
一つ目は「親と自分の間に適切な境界線を引き、親から振り回されたり傷つけたり
しない状況をつくる」ということ、二つ目は「感情を吐き出す」ということでしたね。
「鏡の法則」59ページ
一つ目に関しまして、現在進行形で親からの干渉を受けている方に対して、具体的に物理的な距離を
とること、最も効果的なのは別居することです。
それもままならない場合は食事の時間をずらす、電話やメールを控えてもらう等可能な限り
干渉してくる状況を減らすことが重要になってきます。
ここは勇気を出して親に自分は自分の意思で進んでいくことを伝え、そのために
干渉しないことを約束させることを伝えることが必要です。
自分の気持ちを優先することを意識していきましょう。
二つ目に関してぜひ本書を手に取り読んでみてください。
これらを実践することで他者との境界線が弾けるようになり、最終的には心が軽くなります。
まとめ
本書はずっと心に突っ掛かりを抱えマイナスの状態だった方がゼロへもしくはややプラスへ
なるための指南書になります。
また、子供との接し方に悩まれている親御様へもぜひとも読んでいただきたい一冊にもなります。
本書の特徴としては、抽象的な心の問題がわかりやすいようにより具体的な物語や状況を
合わせて書かれており、また解決策も具体的に記されております。
願わくば自分と向き合うためにも一人一冊は持ってもらいたいぐらいの内容になっております。
おわり
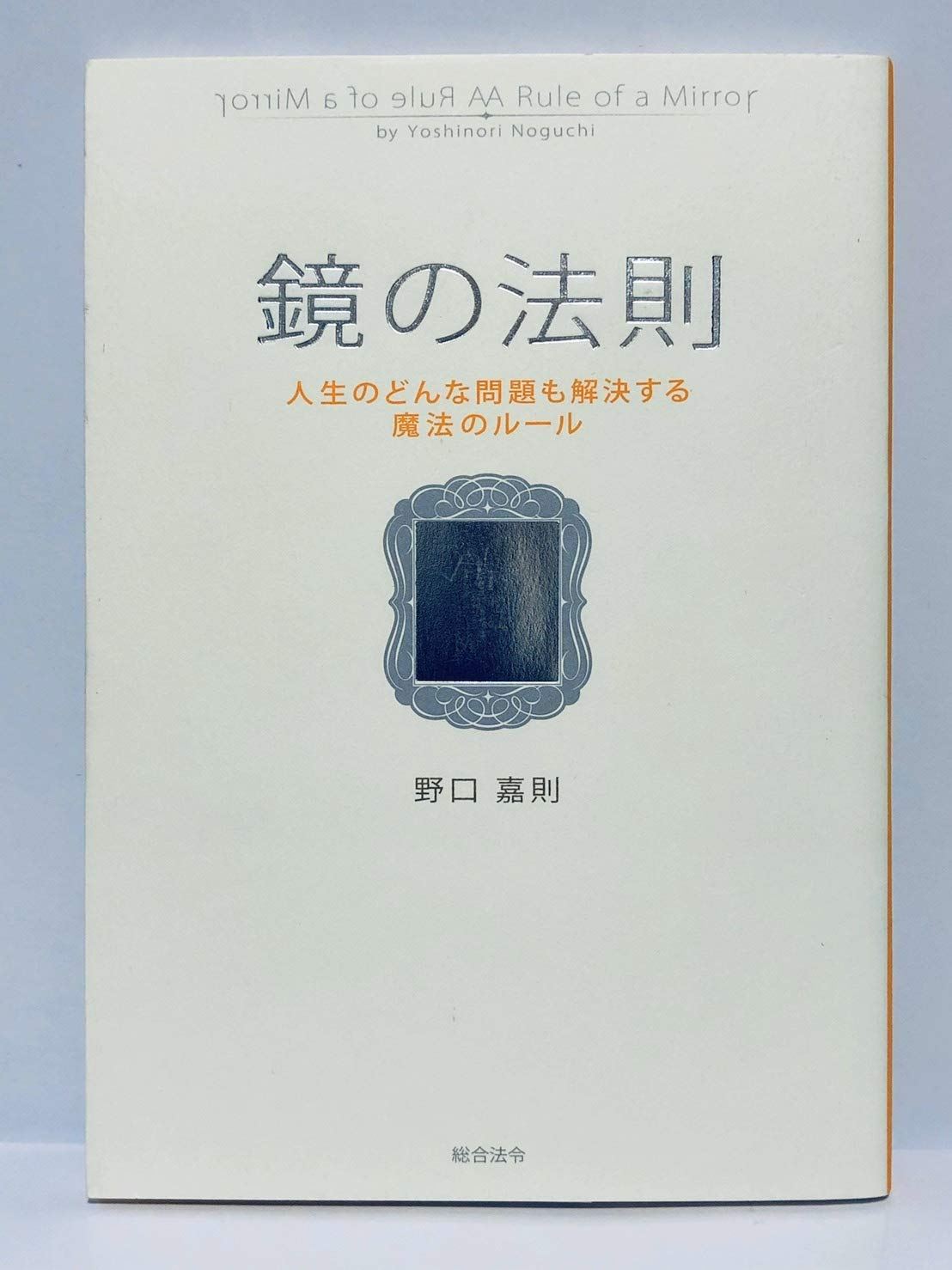


コメント