近年でもないですが、かつての日本よりも転職が当たり前になった時代、自分も転職して
さらに高みを目指すべきか、マイナスな理由で転職をするべきか、大きなタイトルの
一つかと思います。
今回は私の独自の視点から今いる会社を続けるべきか見極めるポイントを選出し、
記事にしていきます。
今の職場を続けるべきか悩んでいる方のほんの少しでも助けになれば幸いです。
この記事でわかること
今いる会社を続けるべきか見極めるポイントがわかる
自分の会社の立ち位置を判断する基準がわかる
転職に対しての考え方は十人十色となかなか難しい題材です。
それでは参りましょう。
5年後、今よりもスキルや資格を習得できるか

この項目はその会社の行ってる業務がスキルや資格など年数を重ねることに自分に付加価値を
与えてくれるものかという見極めポイントになります。
このポイントを押さえられていないと将来的な年収の上昇や仮に今の職場でクビを切られた際に
次の職場に拾ってもらえるか大きく運命を変える要因になります。
単純作業は短いスパンで見れば楽かもしれませんが、それ以上の価値が生まれず、
年齢を重ねれば重ねるほどどの職場や業務に縛られることになりますので、
それこそ一生労働の奴隷となってしまいます。
私の場合、不動産管理会社のため、スキルで言えばお客様に対しての提案力、
現在の業務を見直し効率化を目指すマネジメント力、資格で言えば宅地建物取引士、
賃貸不動産経営管理士等色々なものを身につけて今の仕事に生かすことができますので
この項目はかなり高いレベルでパスしているのではないかなと考えております。
人事評価は直属の上司に属人化していないか
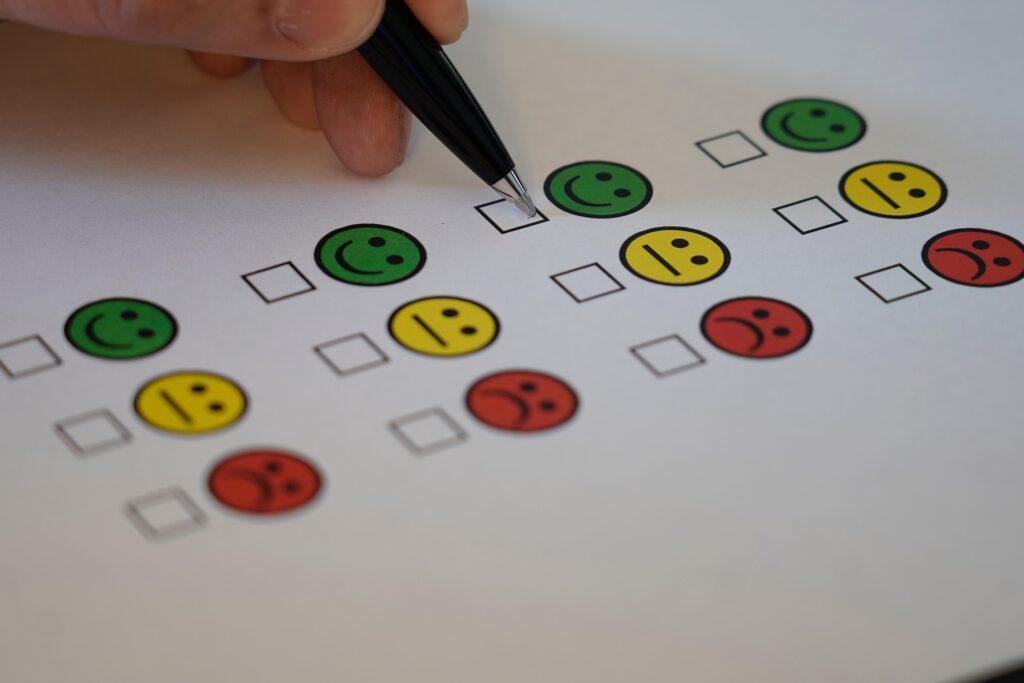
今勤めている職場で昇進を目指す場合、自分はどんな成果を出せばいいのか、どういった
行動や指標に向かっていけばいいのかわかる方は意外と少ないかもしれません。
もちろん自身で把握していないということも往々にしてあるかと思いますが、
それ以前に年に一度の人事評価が直属の上司の感覚で決められていませんか。
もしそうであれば、気に入られたり、顔色を伺ったりして上を目指すことになりますので、
その会社に勤めていくべきかどうか疑問が残ります。
そういった体質の会社の場合、個人の実力よりも気に入られた人が上に立ってしまうため
組織として腐敗していることでしょう。
具体的な成果や目標がしっかり決まっているかどうか、どうしたら昇進できるかどうか
今一度見直してみることをお勧めしたいところです。
先輩社員の年収は将来の自分の希望する金額か

自分と同じ職場の先輩社員の年収は当たり前ですが、将来の自分の年収になります。
今の仕事を頑張ってやっと昇進してもさほど年収が伸びなければ意味がありません。
また、働く気力も減ってしまうことでしょう。
インフレが進む近年、なかなか賃上げも踏み切れない会社も多いかと思いますが、
そもそもの年収が低ければさらに苦しくなることは必至です。
主任、係長、課長、部長、と昇進していたったときいくらぐらいもらえるのか、
可能な限り調べておいた方がよろしいです。
また、平均どれぐらいの期間で昇進できるのか、昇進しようとしているポストは空いているのか
将来空く予定があるのかも併せて確認しておきましょう。
お客様を優先したサービスを提供しているか

入社した頃は右も左もわからずとにかく一日一日の自分に与えられた課題をこなすのに必死。
会社から帰った後や休日は資格やスキルの勉強をし徐々に成長してきます。
そして2年目、3年目と時間を重ねていくにつれて気づいていくのです、
「この会社の提供しているサービスってお客様ファーストじゃなくね?」
よくよく考えればここの契約条項はお客様を縛るものだし、会社が勧めるプランとお客様にとって
本当にメリットがあるプランが違うし‥と徐々に歪みに気がついてくることがあると思います。
多少は企業も慈善事業で商売をやっているわけではないので利益を取るのは当たり前です。
ですが、あまりにも会社の方針と本当にお客様にメリットがあるサービスに乖離があると
お客様に「ありがとう」と言われる度に胸の奥がズキッ、ズキッと痛みます。
その痛みが積み重なっていきいつしか病んでしまったり、モチベーションが下がったりして
退職につながることがあります。
今自分が提供しているサービスはどれほどお客様にとってメリットがあるのか振り返り
今後も自分はそのサービスを提供していくことに対し誇りを持てるか、
一つの見極めポイントにしてください。
新人育成の環境は整っているか

新人育成とは気持ちの持ち方やオリエンテーションなどではなく、その研修を受けていざ
現場に配属された時にある程度一人で働くことができるのかのレベルを指しています。
意外と1〜2週間ほど実戦では役に立たない内容を研修で教え、実務の習得は配属先任せにする
会社も多いのではいかと思います。
なぜ、それがダメなのか、理由は二つあり、一つは新人が入る度にその配属先の誰かが
教育担当になるため瞬間的な負担が増えてしまうことです。
人の入れ替わりが激しい職場であればそんなことをいちいちされては通常業務に支障をきたします。
もう一つは教えた人の技量ややり方で教育するわけですから、教えた人によって新人の
業務の質にムラができます。
そうしますと、方や優秀な新人、方や質の悪い業務をする新人と偏ってしまい、だんだんと
サービスのムラが大きくなり、業務の偏りなどが発生しチームとして不安定になります。
実践的な育成環境が整っているということは具体的な業務のやり方や方針が統一されており
チームとして完成されている証になりますので見極めポイントにしてみてください。
まとめ
今回記事にした内容はあくまでも私個人の判断によるものになります。
一つの判断材料にしてくれれば嬉しいですが、このポイントのみで判断することは
大変危険ですので、多角的な視点で現状の会社を見つめるようにしましょう。
このタイトルは一度では書ききれないほど大きい課題ですので、
もしかしたら今後更に発展させた記事を書くかもしれませんのでお楽しみに
おわり



コメント